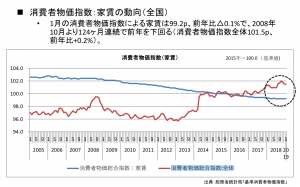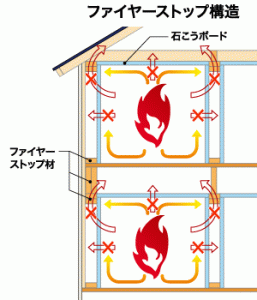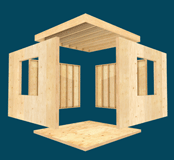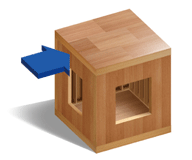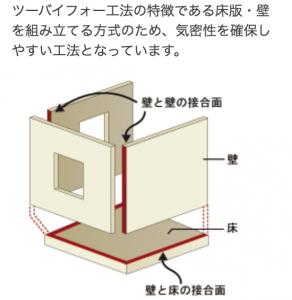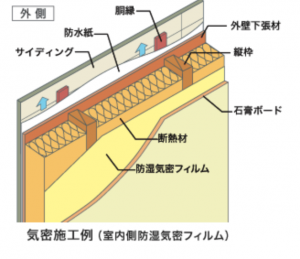公正証書を作成する公証人とは、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、強制執行が可能である公正証書もあります。
公証人は、契約者双方の利害が関係しますのえ、一般的には法律実務の経験豊かな裁判所OBの方が任命されております。
事業用定期借地権では強制執行認諾条項が無いと、単なる賃貸契約書となってしまいます。
双方の権利を守り、安心できる契約関係を保つ為にも、この「強制執行認諾条項」必要なものになります。
公証人が行う公証事務は色々ありますが、公正証書遺言なども代表的な業務になります。
公証事務を行う事務所は公証役場と呼ばれていますが、今の時代、役場という名称も珍しいものです。